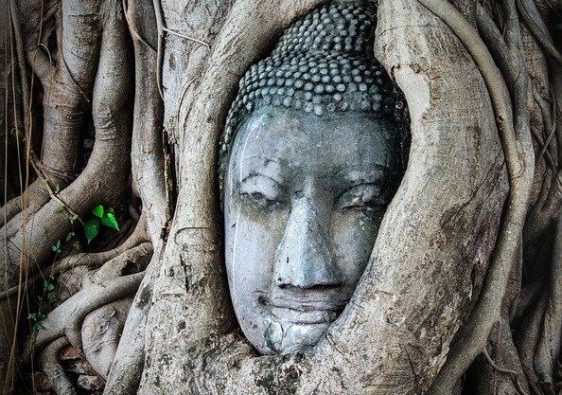お釈迦様は来世について一切説かれなかったと言われることがありますが、たしかにそのような側面はあります。しかしそれは、来世について否定したということではありません。
「十四無記」というものがありますが、お釈迦様は十四通りの質問に対しては答えられなかった、というものです。
その中には「死後も如来は存在するのか」「この世はいつ始まりいつ終わるのか」「霊魂は永遠に存在するものなのか」といった問いがあったようで、このような問いに対してはあまりにも観念的なものとして退けた、というわけです。
しかし、これらの問題は現代でも多くの人々の関心を呼ぶところであり、お釈迦様の弟子からの問いに対して答えないという態度は不遜であるように見えますが、お釈迦様は答えないということではなく答えるべきものではないとされました。
つまりその中にこそ答えがある、ということです。
一休禅師にこんな話があります。
ある方が禅師にこんな質問をしてきました。
「釈尊のお父さんの名前は?」
しかし禅師はこの問いに答えず、ただ大きく口を開けて一言も発しませんでした。質問者はあきれてその場を立ち去りました。
弟子
「なぜ答えられなかったのですか?」
禅師
「あの方にお釈迦様の名前を言ったら、きっと、その前のお父さんの名は?またその前のお父さんの名は?と言うに決まっている。だから答えなかった」
弟子
「ではどうして口を大きく開けられていたのですか?」
禅師
「一休のやつは質問に対して口も開くことも出来なかったと言いふらされてはかなわないから口だけは開けておいた」
このような議論を仏教では不毛な議論という意味で「戯論(ケロン)」と言います。つまり、議論のための議論は「言葉遊び」と言っていいでしょう。
さて、人間が死んだらどうなるのか、という問題ですが
人類発生して以来、様々に追及されてきました。
宗教というものの誕生は「死」の恐れをいかにして超えるか、というところにあると考えます。
お釈迦様以前のインドにも二つの考え方がありました。
一つは「霊魂不滅説」もう一つは「人は死とともに肉体も霊魂も全て消滅して無になる」という考え方です。
前者を「常見」と言い、後者を「断見」と言います。
当時のインド思想からいうと常見の立場が主流でした。
お釈迦様はこの問題をどのように考えられたのでしょう。
無常、無我の教えを説かれたように、すべてのものは一瞬一瞬に形を変えて移り変わるものであり、自己(私)という永遠不変の実体があるとは考えておられなかったようです。
しかし、一切が無に帰するという断見の立場に立つものではなかったのも事実です。
私たちは様々な因と縁によって、はじめてこの世に誕生することができたのです。そして、私の死後も何らかの形で受け継がれていくのです。
決して「無」になることではありません。
死によってすべてのものが無に帰するというのは因果の道理(法則)を無視した考え方でお釈迦様が嫌った思想です。
断見は死について真剣に考える態度を放棄し、自分の人生の責任を回避しようとしている考え方ではないでしょうか。